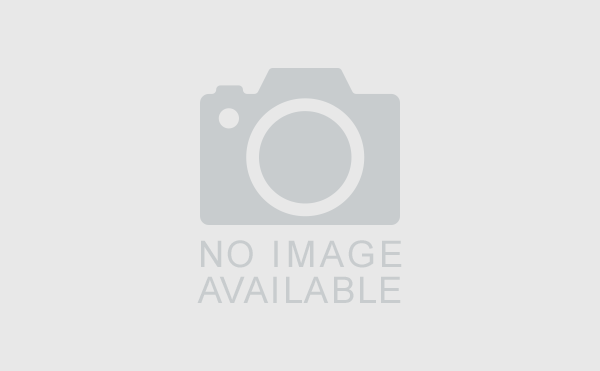子どもの身体の使い方~発達段階を見極め、そこを丁寧にたどっていく~
身体の動きは、胴体の「左右・前後・捻じる・伸び縮み」という動きからはじまり、それが手足の動きに繋がっていきます。
胴体の動きは背骨・骨盤・胸骨の動きの連動でなりたっています。
その部分がちゃんと動けていると、手足もスムーズに動くようになっていくと言われています。
日常の運動をはじめ、スポーツや武道競技をしていると
・頑張ってるのになかなか結果に結びつかない
・練習してるのに技術が向上しない
・苦手が克服できない
という悩みがでてくることがあります。
多くの人は、「テクニックを勉強する」や「筋トレ」で悩みを解決しようとします。
それで解決される人もいますが、テクニックを勉強しても筋トレをしても、おもったように上手くならないし、苦手は苦手のまま根本的な解決にはなっていないように感じることが多いです。
なぜそうなるのか?というと、「身体が使えていない」ということが考えられます。
はじめに書きましたが、身体は胴体の動きからはじまり、それが手足の動きに繋がっていきます。
胴体の動きは背骨・骨盤・胸骨の動きの連動でなりたっていて、そこがちゃんと動けていると、手足もスムーズに動くようになってきます。
体幹を鍛えても、筋トレしても、テクニックを学んでも結果がついてこない場合は、身体の連動が上手くいっていないのかもしれません。
逆に言うと、「身体を使うためのワークを取り入れながら、技術練習や筋トレをすると効果が抜群に現れやすくなる可能性が高くなります。
「身体を使う」とは「運動」ということです。
運動は、固有受容覚や前庭覚、触覚、視覚、聴覚などの身体感覚を、脳が上手に処理することで出来るようになりますし発達していきます。
固有受容覚とは、関節の曲げ伸ばしや筋肉の動きを脳に伝える感覚です。この感覚のお陰で、私たちは無意識のうちに手足や背中など、身体全部の位置がどこにあるのかが分かります。
例えば、固有受容覚の認識が弱いと、自分の身体の位置がハッキリしないので、上手く身体が使えなかったり、人や障害物との距離がつかめずぶつかってしまったり、人の間に入るのも怖くなったりします。
前庭覚は、身体をまっすぐに保つのに必要な感覚です。前庭覚がうまく使えないと、姿勢の自動調整が難しくなります。
このように、「運動器官⇔感覚器官⇔脳・脊髄の情報交換」によって運動ができるようになっていきますし、これは学習にも深くかかわってきます。
つまり、身体を使えるようにしていく土台を整えるというのは、
「運動器官⇔感覚器官⇔脳・脊髄の情報交換を、今よりスムーズにしていく」
と捉えることができます。
では、どのようにして土台を整えていけばいいのか?ですが、
・胎児から赤ちゃんの運動発達
・脊椎動物の移動様式の変化
・動きの発達4段階と原始反射
に着目し段階を見極め、そこを丁寧にたどっていくという考え方があります。
これは、科学的な根拠はありませんが、感覚統合とはまた別の、「動きの発達」「胎児から赤ちゃんまでの運動発達」「原始反射の成長」などといった知見がもとになった考え方です。
子どもたちが
・自分の身体を存分に使い
・やりたいことができるようになる
そのためには、「脳と身体のつながりをスムーズにしていく」ことがとても大事であると、整骨院での施術、指導に係っている柔道クラブ、ふぁみーゆの子どもたちをみていて、日々感じています。
「〇△療育」などという枠をもうけず、「〇◇をすれば治る!」などと偏った考え方をせず、色々な知見や根拠のある情報を取り入れ、統合的にアプローチすることがとても大事だと思います。