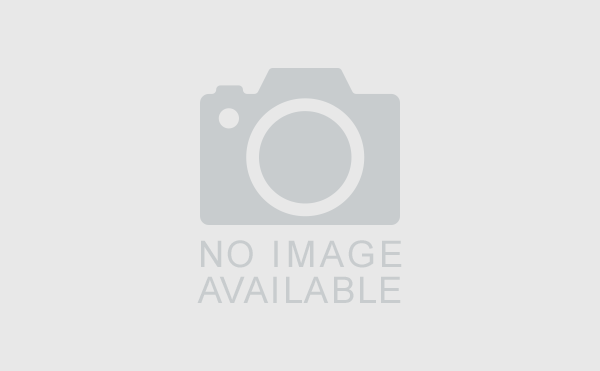4つの基本活動
こども家庭庁が作成した放課後等デイサービスガイドラインには、
・5領域の視点を踏まえたアセスメント(客観的な評価と分析)を行い
・5領域の視点をカバーし
・且つ、4つの基本活動を複数組み合わせながら
子どもたちそれぞれの発達段階と障害の特性に合わせ、オーダーメイドの発達支援(療育)を提供していくことの大事さが書かれています。
今回は4つの基本活動について、ふぁみーゆをご利用いただいているご家族向けに要点をお伝えしていきます。
4つの基本活動
発達支援の本人支援において、目的をもって行動するための4つ指標があり、それを4つの基本活動と呼びます。
4つの基本活動を提供するにあたっては、
・子どもの意見を聴きながら自己選択や自己決定を促す
・子ども同士の関わりの中で、子どもが主体性を発揮しながら参加できる
ように支援していくことが求められています。
それぞれの活動の内容
4つの基本活動には
・自立支援と日常生活の充実のための活動
・多様な遊びや体験活動
・地域交流の活動
・こどもが主体的に参画できる活動
があります。
ガイドラインにはそれぞれの活動の内容が記載されていますので、そのまま引用させてもらいますが、
1,自立支援と日常生活の充実のための活動
こどもの発達に応じて必要となる日常生活における基本的な動作や自立を支援するための活動を行う。こどもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立や地域生活を見据えた活動を行う場合には、こどもが通う学校で行われている教育活動を踏まえ、その方針や役割分担等を共有できるよう、学校と連携を図りながら支援を行う。
2、多様な遊びや体験活動
遊び自体の中にこどもの発達を促す重要な要素が含まれていることから、挑戦や失敗を含め、屋内外を問わず、自由な遊びを行う。また、体験したことや、興味を持ったことに取り組めることは、新たにやってみたいと感じる機会につながることから、多様な体験の機会を提供していく。こどもが望む遊びや体験、余暇等を自分で選択しながら取り組むことができるよう、多彩な活動プログラムを用意する。その際には、個別性に配慮された環境やこどもがリラックスできる環境の中で行うことができるよう工夫することが重要である。
3,地域交流の活動
障害があるがゆえにこどもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないように、地域の中にこどもの居場所をつくりながらこどもの社会経験の幅を広げていく。
他の社会福祉事業や地域において放課後等に行われている多様な学習・体験・交流活動など地域資源も活かして、遊びや体験の機会を創出していくとともに、ボランティアの受入れ等により、積極的に地域との交流を図っていく。こうした取組は、こどもにとって、地域そのものが安全・安心な居場所となることにもつながる。
4,こどもが主体的に参画できる活動
こどもとともに活動を企画したり過ごし方のルールをつくったりするなど、こどもが主体的に参画できる機会を設け、こどもが意見を表明しやすい環境づくりを行いながら、こどもとともに活動を組み立てていく取組を行っていく。その際には、こどもの意思を受け止めつつ、一人一人の個別性に配慮するとともに、こどもに寄り添いながら進めていくことが重要である。こうした取組は、こどもにとって自分自身が権利の主体であることを実感するとともに、こどもの権利を守ることにもつながる。
となっています。